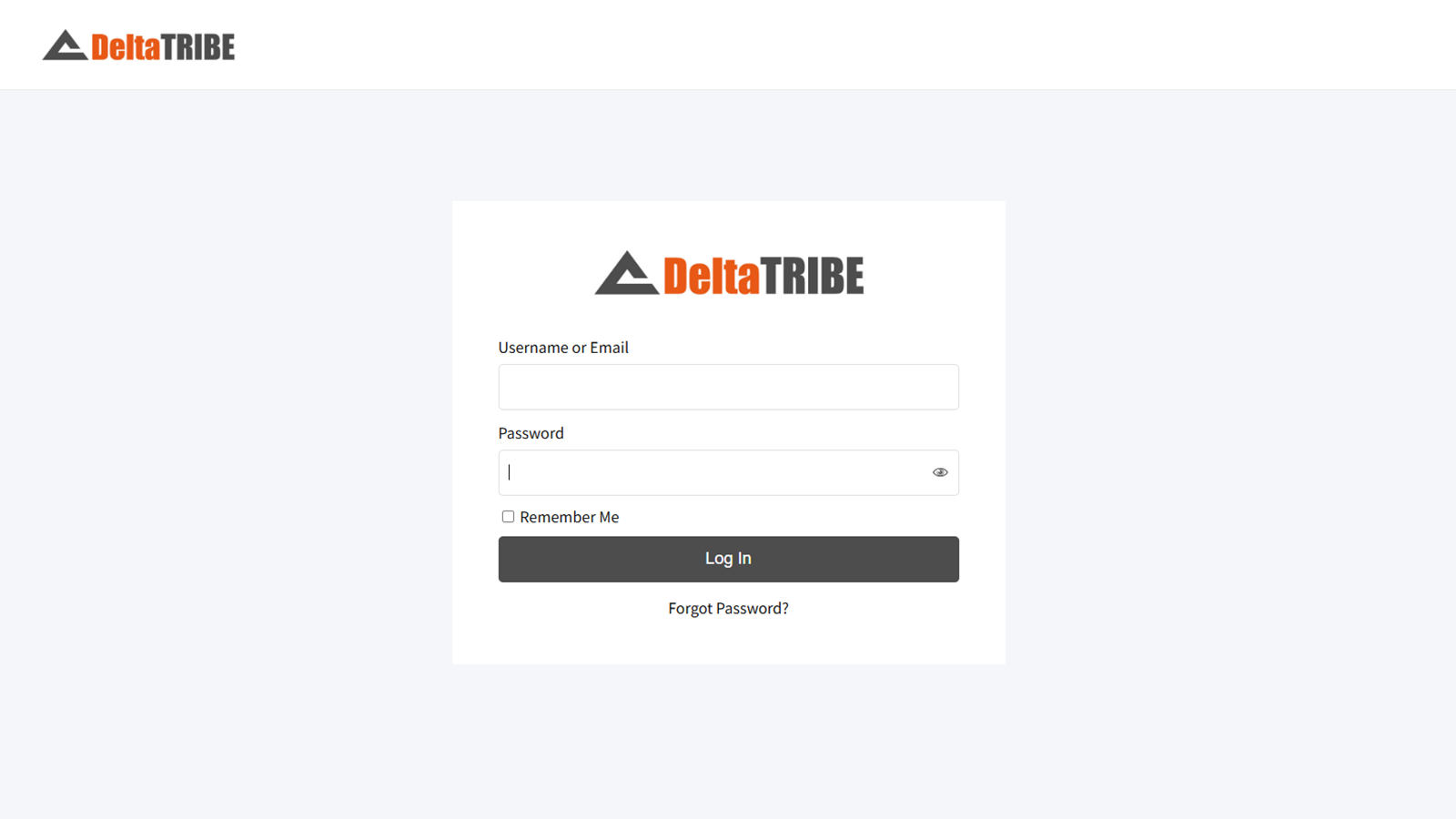Key SEO Trends to Watch in 2024
“Key SEO Trends to Watch in 2024” As we move towards 2024, the world of SEO continues to evolve si […]
2024.01.11
Web Production and SEO Experts Teach: Key Points of Content Strategy [Latest 2024]
The Importance of Web Production and SEO in 2024 Web production and SEO have become indispensable elements for […]
2024.01.05
日本語に対応しているウェブアクセシビリティのチェックツール
日本語に対応しているウェブアクセシビリティのチェックツールもいくつかありますので代表的なものをいくつか紹介します。 これらのツールは、日本語のウェブサイトのアクセシビリティを評価し、問題点を指摘するのに役立ちます。 aX […]
2024.01.05
ウェブアクセシビリティの代表的なチェックツール
ウェブアクセシビリティのチェックツールは、ウェブサイトが様々なユーザーにとって使いやすくアクセスしやすいかどうかを評価するために使用されます。以下は、代表的なウェブアクセシビリティチェックツールのいくつかと、それらの比較 […]
2023.12.28
年末・年始の営業時間のお知らせ
拝啓 今年も師走を迎え、とりわけご繁忙のことと拝察いたします。 日ごろは弊社に多大なご芳情を頂き、厚くお礼申し上げます。 さて、弊社では年末年始の期間、下記のとおり休業期間とさせて頂きます。 休業期間中はご […]
2023.12.25
WCAG 2.1 AAレベルとは
WCAG 2.1 AAレベルは、ウェブコンテンツのアクセシビリティを向上させるためのガイドラインの1つです。 WCAGは、Web Content Accessibility Guidelinesの略称で、国際的な標準規格 […]
2023.12.25
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)とは
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)は、ウェブコンテンツのアクセシビリティを向上させるためのガイドラインです。 WCAGは、国際的な標準規格であり、世界中で広く利用されてい […]
2023.12.22
2024年4月から施行のウェブアクセシビリティとは【4】
ウェブアクセシビリティの普及に向けて ウェブアクセシビリティは、すべての人がウェブを平等に利用できるようにするための重要な取り組みです。 しかし、ウェブアクセシビリティの重要性や、どのような対策が必要なのかを理解している […]
2023.12.20



 JA
JA